http://tamajodo.com/
地元の稽古仲間たちと、ホームページを立ち上げた。2012年7月7日、東京雨、気温22℃、七夕の夜に。

◎杖道の起源は・・・
杖術を併伝武術として継承している流派はいくつか残っていますが、杖術そのものを本技とする流派で、現存するのは四百年前の夢想権之助勝吉という人によっ て創始された神道夢想流杖術だけです。私たちが日頃練習している杖道は、この神道夢想流をベースに昭和43年に全日本剣道連盟が制定した基本12本と、立 合の形12本です。したがって、全剣連杖道を習熟した者はほとんど神道夢想流杖術も併せて稽古するようになります。◎普段の練習の仕方は・・・
杖道の稽古では防具を一切使用しません。そのため普段の練習は、立合の形に基づき行います。打ち込んでくる太刀を捌(さば)き、すかさず杖で太刀の動きを 制するというもので、真剣勝負形でありながらも、相手を傷つけずに勝つという和の精神を持った心の広い武道です。それだけに日頃の練習はもとより試合で も、段別以外には老若男女や体重、身長の違いによる区別はありません。高齢化が進んでも若い人と一緒に楽しめる数少ない生涯スポーツのひとつといえます。(『第23回東京都杖道大会』パンフレットより)

あの大震災(2011/3/11東日本大震災)から3ヶ月がたった。日本は大変な中にあるけど、杖道とともに歩む日日は、ますます面白くて深くてそして、ますますもどかしくもある。
●2011年6月11日土曜日、神道夢想流杖道奥入證、拝受。
金王神社向いの豊栄稲荷神社境内にある藏脩館にて、日本杖道会の神之田常盛総師範から桐箱に入った巻物をいただく。
杖道をはじめて8年、ここに正式入門して2年、古流を修めるスタートラインに立ったよ、ここからは心して一歩を踏み出せよといったところだろうか。
この先、初目録、後目録、免許、免許皆伝に至るのだという。長い時間を経て実際にこの道を歩んだ数少ない師範たち(そうなの、誰でもここまでこれるってわけじゃないの)と日日稽古していると、この流れは進行形の神々しい物語のようにも思える。謎めいた桐箱をそっとあけて巻物を開いてみたりもしたけど、難しい文字列にまごまごするばかりだ。でも、この物語に一歩踏み入った実感は、今、今、今!、師匠たちとの面授の時、稽古の日日の中にある。逃しちゃいけない、精進、精進!
●2011年7月16日の東京都杖道大会、制定形のトーナメント四段の部に出場。この日、おもいがけなく準優勝よ!。わたし、はじめての入賞よ。わお!一度は初戦突破して決勝戦まで上ってみたいもんだと思っていたけどさ・・・。
現代杖道とも云われる制定形は、普及と習熟をめざしてさまざまな工夫がなされているが、そのひとつが大会におけるトーナメントである。
これがちょっとわかりにくい仕組みなんだ。前出の、東京都杖道大会パンフレットp.2、松井健二会長「あいさつ」よりこの辺の事情を抜粋してみる。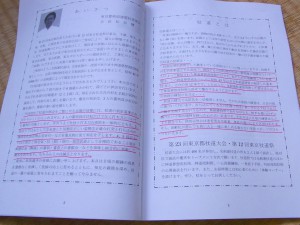
◎では杖道の試合はどのように行われるものでしょうか。本大会では1級以下の部から7段の部まで8段階にわかれて、各段ごとに試合を行います。それぞれ各段の出場選手(2人1組)は、指定された立合の形を2組が同時に演武して、内容の良し悪しを競います。優劣の判定は、3人の審判員が紅白の旗を揚げ、旗数の多い組を勝とします。
↓大会当日の動画、手前の藍色道衣がわたしたち(白組)、奥の白い道衣の女性たちが(赤組)、まずはご覧あれ・・・(Video by SANO Hirokazu)
(抜粋つづき)今回はじめて杖道の試合をご覧になる会場の皆様には、杖道の判定基準がお分かりにくいかもしれません。3人の審判員は仕杖だけでなく打太刀についても審判の対象とします。そのうえで 仕杖と打太刀の攻防を一体的にとらえ、3段以下では主として①充実した気勢②正しい姿勢③正確な打突と打ち込みの強弱④礼法⑤残心⑥目付・・・などを重点的にみて判定を下します。4,5段以上では⑦間合いと間⑧気・杖・体の一致⑨武道として合理的であること⑩全剣連杖道(解説)の審判・審査上の着眼・・・などを加味し総合的に判断して優劣を決めます。もちろんミスは減点となります。
追記:後日、東京新聞に載ったという記事をいただいた。感激!
東京新聞2011年7月17日 、この時点では四段の部優勝、準優勝者氏名に誤りがあったようで、20日訂正記事がでたんだって。それをテープで貼り付けてわざわざプレゼントいただいた。感涙・・・
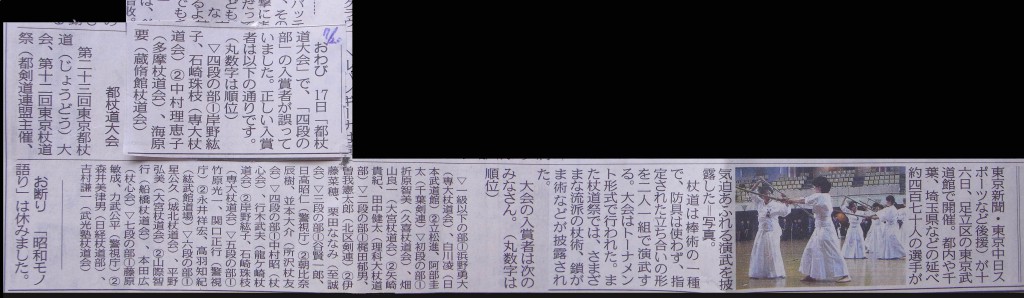
2011年2月20日、武神武甕槌神(たけみかづちのかみ)を祀る鹿島神宮御本殿前にて神道夢想流杖道五本を演武する、日本杖道会主催「平成23年春季武道合宿研修会」にて
打:太田修司×仕:中村理恵子(共に多摩杖道会)
人生が二度ないようにこんな演武の機会も二度とない、身にあまる・・・という言葉をはじめて実感したように思う。
宮司さん、大師匠、先生方、稽古仲間たちの視線の先で、突然のご指名で演武する。
心まっさら、ついでに頭の中も真っ白状態で「はじめ!」の号令がかかる、太刀落(たちおとし)、霞(かすみ)、正眼(せいがん)、雷打(らいうち)、乱留(みだれどめ)。
photo by Mika MIYABARA